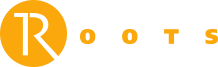ルーツ貿易創業50周年企画 インポーターの視点からふりかえる洋菓子50年 第1回 前編
2026/01/14
東京・尾山台「オーボンヴュータン」河田勝彦シェフ

白根:このお菓子を作るにあたり、ドイツを代表するバウムクーヘンオーブンメーカー、シュレー社のオーブンを導入されましたね。
河田:ドイツの本物を使わなきゃいけないという気持ちがありました。諸説あるようですが、このお菓子、僕はドイツがルーツだと思うんですね。僕が持っている絵葉書に「ナポレオンのロシア侵攻に参加したピレネーの兵隊が旅先で見て、帰郷後に焼くようになったのが始まり」と書かれている。
白根:ドイツでバウムクーヘンオーブンと言えば、シュレー社。視察で向こうのお菓子屋さんを訪問すると、どの店にもシュレー社のオーブンが入っていたものです。
河田:タルブでは、実際に食べて、焼いているところも見ましたが、それまで自分で作った経験がなく、完成までに失敗を繰り返しました。実は現地のものはあまりおいしくないんです。僕はおいしく作りたくて、いろんな配合を試みました。でも、配合が良ければ良いほど、焼き上がりが近づくとドサッと落ちてしまう。細く仕上げる分にはなんとかなるけど、太く焼こうとすると重さに耐えきれず落ちてくる。ところが、19世紀の著名な料理家ユルバン・デュボワによる百年以上前のルセットでやってみたら一発で成功。先人の著作の価値を再認識しました。
河田:ええ。初代は熱源が電気で、生地が乾燥しやすく、工夫を重ねながら約10年使ったかな。バットに水を張って下に置いたり、反射板を取り付けたり。ルーツ貿易の技術者、外井幸男さんには随分お世話になりました。僕の携帯には外井さんの電話番号が登録されているんですよ。
白根:腕の良い職人さんほど道具や機械を大事にされる。メンテナンスしながら長くお使いになりますね。技術者には、うちからお届けした機械じゃなくても、お邪魔した時に、もしお客様が困っていることがあれば見てさし上げるべきだよ、と伝えてきました。
河田:いいことを聞いたぞ(笑)。
白根:2代目からガスオーブンで。
河田:昔、タルブで見たのは、幅が1.5mほどもある暖炉に薪をくべて、生地を人力で回転させながら焼く光景でした。薪で焼くと表面がいい表情になる。移転前の店ではガトー・ピレネーを焼く暖炉を設えたりもしましたね。薪の熱の質なのか暖炉の構造の問題なのか、焼いている間に生地のグルテンが弱まるといったことがあり、使わなくなってしまいましたが。ガトー・ピレネーを焼く時の熱って、凄いんです。最近のバウムクーヘンオーブンはオートマチックで、生地を付着させる作業も機械が自動でやる。でも、うちのは機能が最小限だから、手で流しかける。すると、熱がオーブンの外にも放出されるため、部屋の温度が恐ろしく上がってしまいます。
白根:焼き手のパティシエは大変ですね。
河田:毎年一人に担当させています。表面のゴツゴツした表情をどうやって作るかといったところに、個人の感性が表れて面白い。
白根:窯の火が作り出す表情の引き出し方が問われるわけですね。
河田:何度も焼いているうちに、バティシエの中にこだわりが生まれてくる。それが職人の始まりなのでしょう。
白根:機械を使いこなすにも、職人の感覚が先立ちますからね。
河田:菓子作りはもっと機械化され、やがてロボットて作るようになってしまうのでしょうか。菓子業界に限らず、職人というものが途絶えてしまわないか気掛かりです。

名物菓子はいかに生まれたか

フランス菓子文化を長年探究する「オーボンヴュータン」河田勝彦シェフ。
自らの足でフランス全土を訪ね、歴史を掘り起こしては再現してきました。代表作「ガトー・ピレネー」を焼くのは、ルーツ貿易が納めたシュレー社のバウムクーヘンオーブンです。開発の経緯、道具が支える味づくり、職人仕事の要諦と今後の行方を、ルーツ貿易株式会社 白根康博会長との対談でお届けします。
河田 勝彦(かわた・かつひこ)プロフィール
1944年生まれ。1967年から約8年間フランスで修業し、最後はパリのホテル「ヒルトン・ド・パリ」でシェフパティシェを務めた。帰国後は、埼玉・浦和で「かわた菓子研究所」としてチョコレート菓子や焼き菓子などの卸業をスタート。1981年に世田谷・尾山台で「オーボンヴュータン」を開業。
シュレー社のオーブンを使う理由
河田:古い文献で知って気になり、実物を見たくて、南仏のタルブという町まで訪ねて行ったのが、ガトー・ピレネーとの出会いです。現地では「ガトー・ア・ラ・ブロッシュ(焼き串に刺した菓子)」と呼ばれていました。店を開業して1、2年の頃、日本橋髙島屋から「髙島屋オリジナルの商品を」との働きかけがあり、それに応える形で作り始めたんですね。白根:このお菓子を作るにあたり、ドイツを代表するバウムクーヘンオーブンメーカー、シュレー社のオーブンを導入されましたね。
河田:ドイツの本物を使わなきゃいけないという気持ちがありました。諸説あるようですが、このお菓子、僕はドイツがルーツだと思うんですね。僕が持っている絵葉書に「ナポレオンのロシア侵攻に参加したピレネーの兵隊が旅先で見て、帰郷後に焼くようになったのが始まり」と書かれている。
白根:ドイツでバウムクーヘンオーブンと言えば、シュレー社。視察で向こうのお菓子屋さんを訪問すると、どの店にもシュレー社のオーブンが入っていたものです。
河田:タルブでは、実際に食べて、焼いているところも見ましたが、それまで自分で作った経験がなく、完成までに失敗を繰り返しました。実は現地のものはあまりおいしくないんです。僕はおいしく作りたくて、いろんな配合を試みました。でも、配合が良ければ良いほど、焼き上がりが近づくとドサッと落ちてしまう。細く仕上げる分にはなんとかなるけど、太く焼こうとすると重さに耐えきれず落ちてくる。ところが、19世紀の著名な料理家ユルバン・デュボワによる百年以上前のルセットでやってみたら一発で成功。先人の著作の価値を再認識しました。
手で焼き上げる醍醐味
白根:いまお使いのオーブンは3代目ですね。河田:ええ。初代は熱源が電気で、生地が乾燥しやすく、工夫を重ねながら約10年使ったかな。バットに水を張って下に置いたり、反射板を取り付けたり。ルーツ貿易の技術者、外井幸男さんには随分お世話になりました。僕の携帯には外井さんの電話番号が登録されているんですよ。
白根:腕の良い職人さんほど道具や機械を大事にされる。メンテナンスしながら長くお使いになりますね。技術者には、うちからお届けした機械じゃなくても、お邪魔した時に、もしお客様が困っていることがあれば見てさし上げるべきだよ、と伝えてきました。
河田:いいことを聞いたぞ(笑)。
白根:2代目からガスオーブンで。
河田:昔、タルブで見たのは、幅が1.5mほどもある暖炉に薪をくべて、生地を人力で回転させながら焼く光景でした。薪で焼くと表面がいい表情になる。移転前の店ではガトー・ピレネーを焼く暖炉を設えたりもしましたね。薪の熱の質なのか暖炉の構造の問題なのか、焼いている間に生地のグルテンが弱まるといったことがあり、使わなくなってしまいましたが。ガトー・ピレネーを焼く時の熱って、凄いんです。最近のバウムクーヘンオーブンはオートマチックで、生地を付着させる作業も機械が自動でやる。でも、うちのは機能が最小限だから、手で流しかける。すると、熱がオーブンの外にも放出されるため、部屋の温度が恐ろしく上がってしまいます。
白根:焼き手のパティシエは大変ですね。
河田:毎年一人に担当させています。表面のゴツゴツした表情をどうやって作るかといったところに、個人の感性が表れて面白い。
白根:窯の火が作り出す表情の引き出し方が問われるわけですね。
河田:何度も焼いているうちに、バティシエの中にこだわりが生まれてくる。それが職人の始まりなのでしょう。
職人の感性あればこそ 機械も生きる
河田:僕はメレンゲも手で立てさせたい。10個、12個の卵白を泡立てるのに必要なのは、パワーじゃなくて、手首・肘・肩の使い方です。それは実際にやる中で身体が覚えていくもの。白根:機械を使いこなすにも、職人の感覚が先立ちますからね。
河田:菓子作りはもっと機械化され、やがてロボットて作るようになってしまうのでしょうか。菓子業界に限らず、職人というものが途絶えてしまわないか気掛かりです。

▼インタビュー記事のダウンロードはこちら
インポーターの視点からふりかえる洋菓子50年 第1回 「オーボンヴュータン」河田勝彦シェフ 前編(PDF)